|
バッハの生涯とクラヴィーア作品
「君のもとを離れてこんなにも久しい」「だってキャベツとかぶがぼくを追っぱらったんだ」…『ゴルトベルク変奏曲』の第30変奏にバッハがこんな楽しい2つの民謡をすべり込ませているのをご存知だろうか。しかもこう言い訳をしながら、1時間近くも前に聴いたっきりの最初の楽章が再び姿を現すのだからおかしい。
民謡をいくつか掛け合わせて同時に歌うこのような一種の遊びをクオドリベットというが、この遊び、バッハ家の伝統とも言うべきものだったようだ。16〜17世紀にドイツのチューリンゲン地方に栄えたバッハ家は、年に一度一族で集まって、クオドリベットを即興して楽しむのが習わしだったという。さぞや音楽的な一族であったのだろう。親戚たちは皆そろってこの辺りの町楽師や宮廷楽師、教会音楽家の地位についている者ばかりだ。ヨハン・セバスティアン・バッハは、このバッハ家の一員として1685年3月21日にアイゼナハで生まれたのであった。バッハの生涯を簡単にたどりながら、クラヴィーア作品を概観していこう。
兄のもとを巣立ち国際的な様式を身につける
J.S.バッハの父アンブロジウスはアイゼナハの宮廷トランペット奏者であり、また町楽団の指揮者も務めていた人物である。バッハのすぐそばには宮廷のチェンバリストや教会のオルガニストを務める親戚もいた。ひょっとしたら叔父さんたちに連れられてオルガンを見せてもらったりチェンバロに触らせてもらったりする機会もあったろうし、また父の弟子や出入りする町楽師たちのリハーサルなど、幼いバッハのまわりは音楽でいっぱいであったに違いない。
そんなある日、バッハは突然両親をなくしてしまう。まだ10歳になるかならないかであった。すぐに14歳年上の兄ヨハン・クリストフのもとに身を寄せることになる。この兄は有名なパッヘルベルのもとで修業を終えて、立派にオールドルフのオルガニストを務めはじめていたのだった。オールドルフでラテン語学校に通いながら、ヨハン・クリストフからバッハは本格的な音楽のレッスンを受けはじめたと言われている。
15歳になると親友とリューネブルクに旅立つ。バッハも親友も首尾よく寄宿制の聖ミカエル学校の試験に合格し、聖歌隊員として奨学金を得ながら勉強を続けることになる。この学校の隣は騎士学院で、貴族の子弟にフランス宮廷の礼儀作法などを教えていた。当然フランス人の教師もいたし、すぐそばのツェレの宮廷にはフランスのオーケストラさえ常設されていたという。よく後世の人は、生涯北部・中部ドイツの限られた範囲にしか足を運ばなかったバッハが、どうやってあれほどの国際的な様式を身につけられたかをいぶかしむが、こんなにもすぐそばにそのチャンスはあったのである。
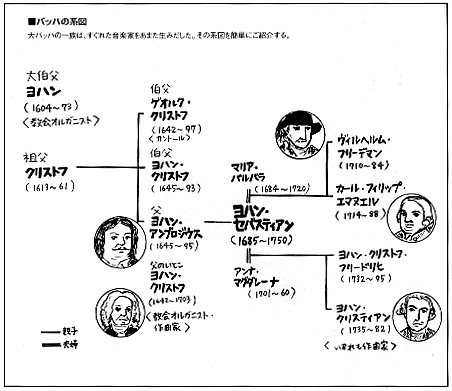
オルガニストとして出発 勉強を重ねる
17歳で卒業し、半年ほどヴァイマルのヨハン・エルンスト公の宮廷楽師を務めた後、8月にはアルンシュタットのオルガニストに就職する。比較的自由な時間の多い職だったので、バッハは自分の勉強に充分時間をつぎ込んだようだ。
20歳の年には4週間の休暇を無断で4ヵ月に延長してリューベックに滞在したことが聖職会議の非難の記録からわかっている。このとき老大家のブクステフーデの音楽に接した体験はよほどショックだったようで、帰ってきて賛美歌を伴奏するのにブクステフーデ風の大胆な不協和音、熱狂的なパッセージをちりばめて会衆を困惑させたらしいということまで聖職会議の記録からうかがえる。22歳の年にはミュールハウゼンにオルガニストの職を得て引っ越すとともに、いとこのマリア・バルバラと結婚式を挙げている。
多彩で魅力にあふれた初期作品群
このころまでのバッハはいったいどんな曲を勉強し、どんな曲を書いていたのだろうか。そのことを考える資料として『アンドレアス・バッハ本』と『メラー写本』という2つの手稿譜集が現在残っている。これらはオールドルフの兄ヨハン・クリストフが編纂したもので、バッハも筆写に参加している。フローベルガーやパッヘルベル、ベームなどドイツのさまざまな作曲家の曲、お隣フランスのオーケストラ曲を鍵盤で弾けるように編曲したものなど、このころの鍵盤奏者のレパートリーと思われるものがぎっしりと書き込まれている。バッハの若き日のレパートリーを想像させてくれる貴重な写本である。
『最愛の兄の旅立ちに寄せるカプリッチョ』、若きヴィルトゥオーゾを彷彿とさせる『トッカータ 嬰へ短調』などバッハ自身の曲もこの手稿譜の中に含まれている。若々しい熱情が駆けめぐるこれらの初期作品の中には、バッハが先人の作品からフーガを熱心に学んだ跡がうかがえるかと思えば、ブクステフーデの影響がみてとれる圧倒的なヴィルトゥオーゾ・パッセージあり、またおしゃれなフランス風の節まわしありと、とても多彩で魅力にあふれている。
家庭も安定 スケールの大きな作品を書く
ミュールハウゼンで1年ほど勤めたあと、バッハはヴァイマル公の宮廷オルガニスト兼室内楽奏者として雇われることになる。給料も増え、キャリアアップは順調である。また、子どもたちが生まれ、家庭も安定してきたようだ。ヴァイマル時代にはオルガン曲やカンタータが多く作曲されたことが知られている。オルガンの鑑定家としてもすでに名高く、あちこちから招聘されている。この時期、ヴァイマル公子が留学先のアムステルダムから持ち帰ったヴィヴァルディら最新のイタリアの協奏曲の楽譜を鍵盤用に編曲したり、またグリニー、デュパールといったフランスの作曲家の作品を写譜するなど、当時のヨーロッパの諸様式に触れるチャンスを生かし、積極的に吸収していったのであった。
このころ完成したと思われる『イギリス組曲』には、その成果が充分に表れていると言えよう。高位のイギリス人に献呈したからイギリス組曲というニックネームがついたという説もあるが、バッハや弟子の間では『前奏曲つき組曲』と呼ばれていたようだ。伝統的なフランスの舞曲組曲の中で、転回対位法、リトルネロ形式、ダ・カーポ形式、ブリゼ様式など、バッハが学んださまざまな書法が、バッハ自身の音楽言語としてみごとに昇華されたスケールの大きな作品である。
悲喜こもごものケーテン時代
さらに32歳でケーテン候レオポルトの楽団の宮廷楽長となる。ついに、ひとつの楽団を率いることになったのだ。音楽を愛する主君に恵まれ、一生をこの地で終えるつもりであったと後にバッハ自身が述懐しているほどのケーテン時代であるが、しかしこの地でも悲しい出来事はあった。レオポルト候の保養地行きに同行している間に、愛する妻マリア・バルバラが急死するのである。
しかし幼い子どもたちを抱えて悲嘆にばかりくれているわけにもいかず、翌年にはソプラノ歌手アンナ・マグダレーナと再婚する。またケーテン時代は教会の任務から離れ、室内楽曲やクラヴィーア曲が多く書かれた時期であった。『半音階的幻想曲とフーガ』はケーテン時代に書かれたと言われる。急死した妻マリア・バルバラへの追悼曲なのではという想像を可能にするほどの激しくほとばしるアフェクト(情念)を支えるのは、強い強いバッハ独自の和声法である。これほどの強靭な受け皿がなければ、あの激烈なパトス(情熱)を支えきれずに散漫な曲になってしまったであろう。
弟子を育て音楽的家庭を築く
『W.フリーデマン・バッハのための音楽帳』の記入開始もこのころと考えられている。バッハが自分の息子にどんな音楽教育を施したのかという点だけでもすでに興味深いが、それに加えてインヴェンションやシンフォニア、『平均律第1巻』のプレリュードなどの初期稿が、異なるタイトルと異なる順番で書き込まれているのが目をひく。
さらに、音楽家であった2人目の妻『アンナ・マグダレーナのための音楽帳』の第1巻には、冒頭に『フランス組曲』第1〜5番が書き込まれている。大きな規模の楽章はないが、精緻でゆたかな書法で丁寧に作曲されている。特にフランスのクラヴサン音楽のブリゼ様式に熟達しているのが顕著だ。
また『平均律クラヴィーア曲集第1巻』の完成もケーテン時代である。すべての調を用いるという発想といい、音楽的内容といい、壮大なこの曲集のファンタジーを後の音楽家たちは常に自分たちの宝としてきたのだ。弟子たちの教育という責務と、音楽的な家庭とがケーテン時代の作品を背後から支えている。バッハ自身がそうであったように、バッハの息子たちも音楽に囲まれて育ち、音楽家への道を歩んでゆく。
ケーテンから新天地ライプツィヒへ
36歳の年に、バッハは大学都市ライプツィヒのトマス・カントル(聖トマス教会の聖歌隊指導者)兼市の音楽監督となり、ケーテンを後にした。
居心地のよかったはずのケーテンを離れた理由として、宗派の問題、子どもの大学教育のことなどいろいろと推測されている。当局との摩擦も多く、決して順風満帆とはいえなかったライプツィヒ時代であるが、結局バッハは65歳でその生涯を終えるまでこの地に留まることになる。
最先端技術も取り入れ佳境に入る作曲活動
ライプツィヒ時代には、当然第一の職務に従って教会カンタータがたくさん書かれるが、そのかたわらでバッハは自費出版のかたちで自分のクラヴィーア曲を世に送り出す。出版というのはライプツィヒのような開かれた都市でこそ可能であり、最先端技術の波にバッハもちゃんとのっかっている。自分の芸術をより多くの人に伝えたいという想い、そしてそれが礼拝での奏楽という用途のはっきりとしたオルガン曲ではなく、愛好家を含めた不特定多数の人々に向けたクラヴィーア曲であることに新しい時代の動きを感じることができよう。
まずは6曲のパルティータを、第1番変ロ長調(1726年)から始めて6番まで1冊ずつ分冊で売り出し、1731年には6曲まとめて1冊の『クラヴィーア練習曲集 作品1』として出版することになる。1725年(40歳)の『アンナ・マグダレーナのための音楽帳第2巻』の冒頭にすでにパルティータ第3番と第6番が記入されているから、作曲の順が出版の順に反映されているかは不明だが、組曲の歴史の中でもひとつの頂点をなすこの曲集は、常識を遥かに越えて技術的にも内容的にも濃い、とてつもないものとなっている。
宗教的声楽作品の作曲も佳境に入ってくる。ヨハネ、マタイの両受難曲が次々に初演されるほか、カンタータ作曲の充実ぶりも知られている。一方、コレギウム・ムジクムの指揮者に就任したことで、教会を離れた新たな活動の地平も開けてゆく。テレマンによって創設されたこのコレギウム・ムジクムは大学生を中心とした演奏団体で、コーヒー・コンサートなど教会の外で市民のための新しいコンサート活動を繰り広げていたのだった。
1台から4台までのチェンバロのための協奏曲は、このコレギウム・ムジクムのために書かれたと言われている。息子や弟子たちとともに、バッハ自らもソリストとして活躍したのであろう。
人々の理解を得てみごとな成果を上げる
また、このころから聖職会議との軋轢はいっそう高まっていたようだ。現在残っている資料はその様子をかなり詳しく伝えているが、問題は複雑で根が深い。出世した旧友、エルトマンに宛てた手紙も残っており、その中でバッハはライプツィヒでの窮状を訴え、転職の斡旋を頼んでいる。
それに比べ、教会の外でバッハの芸術を理解する人は確実に増えてきたようだ。50歳の年にはパルティータに続く『クラヴィーア練習曲集第2部』として、『イタリア協奏曲』と『フランス風序曲』がセットで出版されている。当時のヨーロッパを席巻した2大管弦楽スタイルを何とか鍵盤楽器の書法に取り入れることはバッハの若いときからの関心事であったが、そのみごとな成果のひとつと言えよう。特に『イタリア協奏曲』は当時から大人気だったようである。
さらに『ゴールドベルク変奏曲』が4つめの『クラヴィーア練習曲集』として出版されたのは、バッハが56歳のころである。不眠症に悩むカイザーリンク伯爵からの依頼によって作曲されたというのは、バッハの伝記作者フォルケルの伝えるエピソードだ。『平均律第2巻』の完成もこのころだと言われている。ますます楽器が美しくそして変幻自在に響く書法のプレリュードと、より多彩で個性的なフーガがちりばめられ、充実した内容となっている。
この時期のバッハは、生涯の中で他のどの時期よりもチェンバロという楽器にこだわっているようだ。この楽器の魅力をあますことなく引き出すことに夢中になって筆を走らせている。
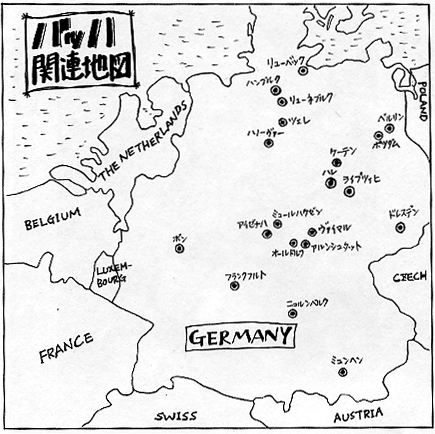
脈々と継がれてゆくバッハ家の血
次男のカール・フィリップ・エマヌエルがチェンバロ奏者として勤めていたポツダムのフリードリヒ大王の宮廷を訪問したのは、62歳のときである。このときの即興演奏がきっかけで、『音楽の捧げもの』が作曲された。このとき新興の楽器ピアノ(ジルバーマン製)も弾いている。
一方、死の直前まで取り組んでいたと言われる『フーガの技法』がいったいいつごろから作曲されはじめたのかはよくわかっていないが、この不思議な作品が、クラヴィーアによる演奏を第一に想定して書かれているということがこれまでの研究で明らかになってきている。バッハが最後に書いた曲はいったい何であったのだろうか。
くしくもヘンデルと同じテイラーという医師によって2度目の手術を受けた後、1750年6月28日午後8時過ぎにバッハは息を引き取ったと言われる。65歳であった。すでにバッハの息子や弟子たちは音楽家として活躍を始めており、その名声は高く、バッハ家の血は脈々と受け継がれてゆくのであった。

フルートを吹いているのは、音楽を愛したことでも知られたフリードリヒ大王。
チェンバロを弾くカール・フィリップ・エマヌエル・バッハは、長年大王の宮廷に仕えた。
ポツダム、サンスーシ宮でのこの演奏会には、大バッハも招かれて出席したという。
この絵は後世の画家A・メンツェルの筆になるもの
知っておきたいバッハの身近な楽器
最後に、クラヴィーアという言葉について触れておきたい。鍵盤楽器という広い意味でオルガンを含むこともあるが、バッハのころ、ふつうにはチェンバロとクラヴィコードを指すと思っていい。バッハにとってオルガンは公の楽器であり、家ではクラヴィーア、つまりチェンバロやクラヴィコードを弾いていたと思われる。
バッハがオルガンやチェンバロをよく演奏したり、そのための曲をたくさん書いたことは広く知られているが、意外に知られていないのがこのクラヴィコードという楽器。チェンバロよりもずっと安く作れるとあって、当時のオルガニストたちは若いころからみな練習用に持っていたと言われている。鍵盤を押すとその先についている小さな金属片が弦をそっと押して音を出すという実に単純な、しかし微妙なしかけの楽器なのだ。当然音も小さく、練習にはもってこいだ。
しかしそれ以上に重要なのは、この弦を押して音を出すという仕組みのせいで、強弱も自在で、まるで弦にじかにふれて弾いているかのような感触があることだ。このことが鍵盤奏者の指をどれほど敏感にしてくれるかわからない。「カンタービレを学ぶために」とタイトルにあるインヴェンションはなによりもこのクラヴィコードでの学習を思わせるし、「打鍵の最高度の明快さ」の秘密としてフォルケルが詳しく描写しているバッハの指のテクニックはまさにクラヴィコードのものだ。
今年はバッハの年。このクラヴィコード、そしてオルガン、チェンバロといったバッハのそばにあった楽器たちをぜひ聴いたり、触ってみたりしてお試しあれ。バッハの世界により近づけることうけあいである。生きていたころのバッハにもっと近寄ってみたいと思われる方にもうひとつお勧めしたいのが、バッハ叢書(白水社)第10巻の『バッハ資料集』だ。バッハをめぐる手紙、証言など当時の様子を想像する手がかりがたくさんつまった楽しい本である。
これらの資料から直接あなた自身で、バッハの生涯や作品についてのイメージを組み立ててみてはいかがだろうか。
『ショパン』2000年1月号・2月号
|