|
楽譜どおり弾かない音符!?
「今日はいいお天気です」…と言う時、われわれ日本人は3文字目の「は」をwaと発音します。私たちにとってはあまりにも当たり前ですが、日本語を学ぶ外国人にとっては「なんで?」というものらしいのです。その「ことば」を話す人たちの間では暗黙のうちに了解されている「習慣」のようなものに戸惑われた経験はありませんか? じつは古い時代の音楽にもいくつかそういう「習慣」があることが知られているのです。
例えば、バッハが大変敬愛していたことでしられるF.クープランのチェンバロのための教則本(1716年)には、こんな文章が載っています。
…私に言わせれば、我々の[フランスの]音楽を記す方法には、言葉を表記する方法にあるのと軌を一にする欠点がある。つまり、我々は、実際の演奏とかけはなれた記譜を行っているのである。我々が外国人の音楽を演奏するのに比べて外国人が我々の音楽を演奏するのが下手なのは、そのせいなのである。反対に、イタリア人たちは、自分が考えたとおりに正しい音価で音楽を書いている。例えば、我々は、数個の順次進行の8分音符を、付点がついているように演奏するが、これを書くとなると、同じ音価のものとして書く。我々は習慣にしばられ、それを守っているのである。(『クラヴサン奏法』F.クープラン著、山田貢訳、シンフォニア)
これは、ちょうどジャズ奏者たちがするスィングのようなもので、不均等奏法とかノート・イネガルなどと呼ばれるものです。ときどきピアノで弾かれるクープランやラモーなどクラヴサン用の曲を弾く時には、この奏法をよく用います。フランスの作曲家だけでなく、バッハのように、小さい頃フランス人舞踏教師に連れられて、フランスの楽団を聴いたりフランス風の舞曲を習うなど、フランス音楽の影響を強く受けた作曲家の作品にも当てはまる可能性があるともいわれています。まあ、バッハの作品すべてが不均等奏法で、というのは考えにくいとしても、もし当てはまる曲があるとすれば、どの曲のどこで?といいうのは考えてみる必要がありそうです。
もう少し当時の教則本を眺めてみましょう。
…ゆっくりしたアッラ・ブレーヴェ、または4/4で下拍に16分音符がきて、その後に付点音符が続く場合は、休符には付点か、またはいま1つ半分の長さの休符がつき、その後の音符には鉤がもう一つ余分についているかのように想定しなさい。(『フルート奏法』クヴァンツ著、荒川恒子訳、全音楽譜出版社)
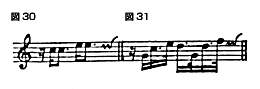
これは、オーケストラの音楽でよく問題になります。バッハのクラヴィーア作品でもオーケストラ作品の様式で書かれた曲、例えば《パルティータ第2番
ハ短調》の第1楽章(譜例4参照)などはこの例に当てはまると考えられています。
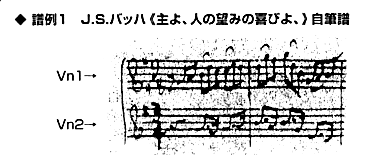
3連符と付点音符が同時に書かれている場合
また、マイラ・ヘスの編曲で有名な《主よ、人の望みの喜びよ》を弾かれたことのある方はいますか? この曲の原曲、バッハのカンタータ147番のスコアで第2ヴァイオリンのパートをみると、譜例1のように記譜されています。この付点の後の16分音符を3連符の3つ目の音に合わせてあたかも
 のように弾くという習慣については、バッハの次男、カール・フィリップが次のように述べています。
のように弾くという習慣については、バッハの次男、カール・フィリップが次のように述べています。
…いわゆる普通拍子つまり4分の4拍子において、さらには4分の3拍子や4拍子においても、三連符が頻繁に用いられるようになって以来、今あげた拍子ではなくて、8分の12拍子なり9拍子なり6拍子としたほうがむしろ便利であるといった曲に多く出会うようになっている。そこで譜例177にみられる音符は、他の声部との関係で、そこに記されている通りに奏される。こうすることによって不快なことが多く、演奏も決まって難しい後打音は避けられるのである。(『正しいクラヴィーア奏法』C.P.E.バッハ著、東川清一訳、全音楽譜出版社)
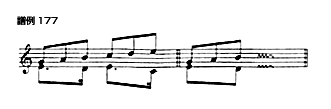
それでは、3連符と同時に書かれている付点音符はいつでもそう奏されるべきなのでしょうか。バッハの弟子、J.F.アグリコラの意見を聴いてみましょう。
…三連音符に付点音符が対応している場合には付点音符のつぎにくる音符が三連音符の三番目の音符と合致するように弾くこと、という教則が70ページにある。だがこれは非常に速いテンポの曲の場合にしか当てはあらない。(中略)こんなふうにJ.S.バッハは彼の弟子たちすべてに教え…(『バッハ資料集』酒田健一訳、白水社)
いったいどの曲が「速いテンポの曲」なのか、自分で判断するしかありませんが、筆者の場合、バッハの《パルティータ6番》の〈テンポ・ディ・ガヴォッタ〉(譜例2)のような例では、付点後の16分音符を3連符に合わせ、例えば《ヴァイオリンとチェンバロのソナタ
第4番》の第3楽章(譜例3)のようなゆったりとした曲では合わせず、音価どおり、というふうに考えています。
先に引用したクヴァンツの『フルート奏法』の中にもこの問題について書かれた箇所があります。ぜひご自分で探し出してみてください。
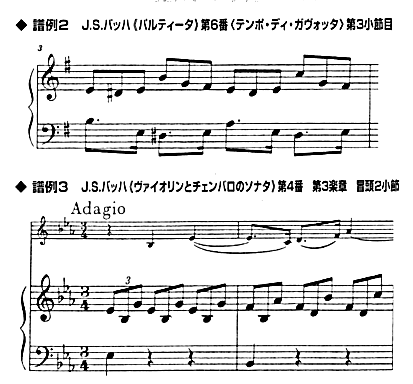
付点を複付点のように弾く場合
また、よく話題になるリズムの習慣の問題に、付点を複付点のように演奏する、というものがあります。
…点[付点音符]に続く短い音符はつねに、その音符の時価が要求するよりは短く奏される。…(中略)…このようにいろいろな場合があるので、すべてを正しい演奏どおりに記譜するのが一番である。しかし、そのように記譜されていない場合にも、曲の内容からその奏法に関して多くの示唆を得ることができる。(『正しいクラヴィーア奏法』)
…というのは、付点のあとの短い音は本来正確に決定することができないからである。(『フルート奏法』)
同時に、これらの教則本に出てくる「規則」を安易にさまざまな作品に当てはめてしまうことに、警告を発している『正しい装飾音奏法』(F.ノイマン著、為本章子訳、音楽之友社)のような意見もあります。筆者の場合、ノイマンの論にそのまま賛成できないところもたくさんありますが、それでも18世紀の資料を読むときの問題点を色いろ気づかせてくれる本です。
参考になる当時の教則本
18世紀の啓蒙主義の時代になると、より多くの人に音楽芸術の秘密もわかりやすく伝えたい、という思いが強くなったのか、さまざまな楽器の奏法や演奏上の習慣を解説した本が多くなります。ところが、概して演奏法を原則論的に解説しようとしても例外やあいまいな箇所が多く残ってしまうものですし、場合によっては同じ時代に同じ国で、全く正反対のことが主張されることだってあるのです。また、その著者がどういう経歴や考え方の持ち主で、より保守的なのか革新をめざしていたのか、またその本は誰を念頭においてかかれたものなのか(初心者に向けて書かれたものなのかなど)、によって読み方や適応範囲が変わってくる場合もあります。ですから、それが昔のものだからといってすなわちすべて「正しい」とか、同時代のすべての作品に当てはまる、というわけではありません。しかし、そのような難しさがあることを知っていただいた上でなお、やはり弾く人それぞれが直接当時書かれたものから情報やヒント、インスピレーションを得て、考えてみることは重要なことではないでしょうか。バロック時代から古典派にかけての教則本には、日本語で読めるものだけでも別表にまとめたように出版されています。そこに「正しい」ことが書かれてあるとかないとかということとは別に、ぜひ一度目を通されることをおすすめします。
結局のところ、「楽譜どおりに弾かないリズム」といわれるものも、「規則」と呼べるほど確実にわかっているものではないです。当時のさまざまな手がかりを頼りにしながらも、どのやり方でならその音楽が本来の姿で響くのか、常に奏者が判断していかなければならないのではないでしょうか。
日本語で読めるバロック時代から古典派にかけての教則本
●F.クープラン:クラヴサン奏法(山田貢訳、シンフォニア)1716年
●J.J.クヴァンツ:フルート奏法(荒川恒子訳、全音楽譜出版社)1752年
●C.P.E.バッハ:正しいクラヴィーア奏法(東川清一訳、全音楽譜出版社)1753年
●L.モーツァルト:ヴァイオリン奏法(塚原晢夫訳、全音楽譜出版社)1756年
●P.F.トージ/J.F.アグリコラ:バロックの声楽技法(R.クライン、小椋和子、シンフォニア)1757年
●D.G.テュルク:クラヴィーア教本(東川清一訳、春秋社)1789年
『ムジカノーヴァ』2006年10月号
|