|
むかしの鍵盤楽器での「音づくり」
〜チェンバロ、オルガン、クラヴィコードに触れてみよう
弦楽器奏者のように自分の指でヴィブラートをかけられる鍵盤楽器があるのをご存じですか? 知っておられる方も多いでしょうが、答えはクラヴィコード。バッハやモーツァルト、ハイドンが愛奏していたことで知られていますが、聞き伝えられるところではショパンやワーグナーも弾いていたとのこと。鍵盤の先につけられたマイナスドライバーの先のような形をした金属片(タンジェントといいます)が、弦を「押して」音を生み出します(図1)。当然強く押せば強い音に、しかも張力が上がるので音程がやや高くなります。これを利用して鍵盤に加える圧力を増減させると指でヴィブラートがかけられるのです。これは言い方を変えれば、指の圧力のばらつきもそのまま音程や音量に反映されるということで、とても繊細な指のコントロールが必要となります。しかも音が出ている間中ずっとタンジェントを通して奏者の指は弦の振動を感じています。このことから、指を敏感にし、表現力を増すためにはぜひクラヴィコードで練習するようにと、むかしから奨められてきたのです。
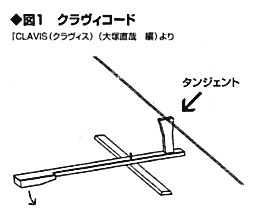
クラヴィコード&チェンバロ
例えば、バッハの次男カール・フィリップの教則本『正しいクラヴィーア奏法』の第1部のはじめの方にこんな記述があります。
――本来からするとクラヴィーア奏者すべては、よいフリューゲル(訳注、チェンバロのこと)とよいクラヴィコードの両方を持たなければならない。もちろんそれは、どの曲も両方の楽器で交互に演奏することができるようにするためである。クラヴィコードで上手に演奏できる人は、フリューゲルも上手に演奏するが、その逆も真なり、とはならない。したがってよい演奏表現を習得するためにはクラヴィコード、必要な指の力をつけるためにはフリューゲルを用いなければならない。いつもクラヴィコードばかり弾いていると、フリューゲルで上達するには、多くの困難に出会うことになろう。(中略)他方フリューゲルばかり弾いていると、一色で演奏することに慣れっこになって、すぐれたクラヴィコード奏者だけがフリューゲルで出すことのできる種々様々なタッチが埋もれたままに終わってしまうことになる。このように言うと、どの指もフリューゲルでは同じ音を出すしかない、と考えている人には奇妙に聞こえるかもしれないが、これについては、簡単に実験することができる。よいクラヴィコードを弾いている人と、フリューゲルばかり弾いているもう一人の人に、同じフリューゲルをつかって同じ曲を、同じ装飾音をつけて、相次いで演奏してもらってから、その二人がはたして同じ効果を生んだかどうかを判断するのである。(『正しいクラヴィーア奏法』C.P.E.バッハ著、東川清一訳、全音楽譜出版社)
つまり、チェンバロは無表情にしか弾けないとみんながおもっているけれど、じつはタッチで表情がこんなにつけられる、とカール・フィリップは言いたいのでしょう。それには、指を敏感にするクラヴィコードで練習した方がよい、ということです。ご存じのとおり、チェンバロの発音は、小さなつめ(むかしは鳥の羽軸、今はプラスチックのものが多い)で弦をはじきます(図2)。はじめてチェンバロに触る人のレッスンで、2つや3つの音をディミヌエンドしてみる、という練習をすると、「チェンバロでは強弱はつかない、ときいていたのに……」と皆さん驚くのです。そしてやっているうちに、はじくスピード、そしてごく小さな「つめ」のしなり方を指で感じ取ろうと、指の感覚がどんどんとぎすまされていくのを体験することができるのです。この感覚をもとにさまざまなニュアンスのある音を作っていくのですが、これこそまさにカール・フィリップのいう「フリューゲルで出すことのできる種々様々なタッチ」にほかなりません。
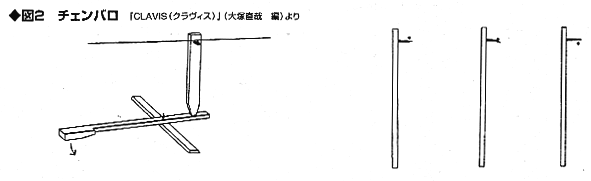
オルガン
オルガンではどうでしょうか。オルガンはチェンバロやクラヴィコード、ピアノなどの有弦鍵盤楽器とは違って「管楽器」です。指は鍵盤を操作することによって、パイプに送られる風をさえぎる「弁」を開け閉めすることになります(図3)。なかでも、「弁」を閉めるときのやり方(リリースといいます)によって音の印象がしまった感じになったり、丸みを帯びたりと、だいぶ変化することが知られています。ですから、オルガニストも発音するときのタイミング、リリースするときのタイミングなどを微妙にコントロールして「音づくり」をしているわけで、むかしながらのアクションを持つオルガンでは、弾く人が変われば当然音も変わってくるのです。
さらに面白いことに、オルガンのこういったタッチを何かの機会に真剣に勉強したピアニストやチェンバリストはその後たいてい、ピアノやチェンバロの音がきれいになるといわれています。これはオルガンを弾くことを通してリリースにも意識を向けるようになるということがその大きな要因だと思われます。そういえばさきほどのカール・フィリップも、チェンバロがうまくなるためにはクラヴィコードを、といっていました。ある楽器をうまくなるためには、別の楽器を練習した方がいい、というのを不思議に思われる方もいるかもしれませんが、かつての鍵盤楽器の世界では当然のことだったようです。すなわち、かつては、オルガンやチェンバロ、ピアノのように、タッチの違うものを一人の鍵盤奏者が弾き分けるものであったのです。いったいどんなテクニックを彼らが持っていたのか、いろいろ調べてみると、その基本のひとつは、「なるべく発音点のそばに指をおいておく」ということであるようです。このことによって、楽器ごとに違う「発音のくせ」に対応して、それぞれの楽器の個性に合わせた形での「よい音づくり」が可能になる、そんなテクニックをどうやら大事にしていたらしいと思われるのです。

響く「つぼ」を探す感覚を研ぎ澄まそう
ところで、考えてみると「よい音づくり」とは何なのでしょうか。そういえば、高校生のとき、ピアノの先生に耳にたこができるほど「音を聴きなさい」といわれたことを思い出しますが、これが「音づくり」の出発点であることは間違いありません。汚い音を出さないようにする、とか、各声部のバランスを考えていく、などといろいろな言い方で「音づくり」について語ることができますが、さらによくよく突き詰めてみると、結局のところ、自分が出したい音のイメージがあること、そしてそれをどんなふうに「キー」に働きかけたらその音が出るのか、その音の出る「つぼ」のようなものを探し当てること、というようにいうのが、妥当である気がしてなりません。普段自分が練習しているピアノと試験やコンサート会場のピアノのタッチが違い、この響く「つぼ」も違う苦労は皆さんよくご存じだと思いますが、チェンバロやオルガン、クラヴィコードといった楽器をむかしの鍵盤奏者が弾き分けていたときに使っていた感覚というのもまったくそれと同じで、まさに一つ一つの楽器のキーの個性、すなわち鳴る「つぼ」がどこにあるかを探す感覚なのです。電子ピアノやサイレントピアノなどの楽器が、アコースティックな楽器(ピアノなど)の練習にはならない、と言われることがありますが、それはこの響く「つぼ」を探す感覚が鈍ってしまうからにほかなりません。
この感覚を研ぎ澄ますには、いつも同じ楽器を触っているだけでなく、たとえばクラヴィコードやチェンバロ、オルガンなどほかの発音原理による鍵盤楽器を触ってみるのも大事でしょう。また同じピアノでも、18世紀のピアノ、19世紀前半のドイツのピアノ、19世紀中ごろのフランスのピアノ、などいろんなピアノを日本でも触ることができるようになってきました。練習が煮詰まってきて音づくりがよくわからなくなってきたり、響く「つぼ」を探し当てる指の感覚をより育てたいと思われる方は、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。なぜなら、歴史上の鍵盤の名手たちはみなそうして、優れた「音づくり」をしてきたのですから。
『MUSICA NOVA』2007年7月号
|