|
レッスンしましょ!
今月の曲 ロンド 《カッコー》 ダカン作曲
〔標準版〕 『バロック・アルバム1 36の小品集』 原典版(音楽之友社)
カッコーの鳴き声をピアノで真似てみよう!
自然の描写を好んだ当時の人々
この現在でも人気の高い《かっこう》は、フランスで有名なオルガニストとして名を馳せたルイ=クロード・ダカンが、1735年にチェンバロ(クラヴサン)のための曲集の中で発表したものです。ダカンはバッハやヘンデルより9歳年下の1694年生まれ。つまりクープランやラモより少しあとの世代の作曲家で、今ではオルガンのための曲がよく知られています。
彼が生きていたころは、「自然」に対する特別な敬意や憧れを持っていた時代で、絵画で風景画を描くように、音楽でもたくさんの自然の描写が試みられました。「鳥の声」は特に好まれた題材で、例えばクープランの《恋のウグイス》、ラモの《めんどり》、そしてこのダカンの《かっこう》など、現在でも演奏される機会の多い名作も生まれています。ぜひ一度チェンバロ(クラヴサン)での演奏も聴いてイメージを作っていただくことをお勧めしたいと思います。
「ロンド」の魅力
さて、この曲の冒頭に書かれている「ロンド Rondeau」という言葉は、この曲の構造をあらわしているものです。「ロンド」はこの時期のフランスの作品の中でよく用いられる形式で、テーマとでもいうべき「ルフラン(=“繰り返し”の意)」の間に、それぞれ個性的な挿入部とでもいうべき「クープレ」が挟み込まれていきます。
この曲の場合も、
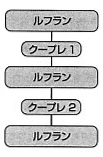
という進み方をしてゆきます。
「ロンド」の場合、それぞれの「クープレ」を、いかにうまく性格付けて演奏するかも面白いのですが、同じ音楽のはずの「ルフラン」が違う「クープレ」のあとにやってくると、先ほどとは違う側面に光が当たったかのように別の雰囲気をまとって聞こえるのも、魅力のひとつです。おまけにこの「ルフラン」は一度さらってしまえば、それを何回も曲の中で使えて、その分音楽を楽しむ余裕が出るのでとてもお得。このあたりにも好まれた理由があるかもしれません…。
一見シンプルな、しかし「技あり」の音符たち
この曲はほとんどの箇所が、右手と左手がそれぞれ1声ずつの2声を基本として書かれており、リズムも単純に見えますが、しかしそこは鍵盤の名手であったダカンのこと、シンプルな中にもさまざまな工夫が凝らされています。
例えば、冒頭のホ短調の主題は、途中でト長調(②)、ロ短調(③)に転調され、指の運び具合はそれほど変わらないのに、まったく違う響きを楽しむことができるようになっています。全体に和声や調の配置に、さりげなくも繊細な配慮があちこち見られますが、弾く上では終止形(あちこちにある☆印の箇所)をしっかりと意識して、それぞれのセクションをていねいにまとめることが必要でしょう。
また、冒頭で左手の「カッコー」(①)を伴奏する右手の16分音符にも、カッコーのテーマが隠されていますが、このように16分音符の連続の中にさまざまな模様が隠されている可能性があります。カッコーのテーマなら少しほかの音より響かせてもいいですし、またそうではない場所では、例えば

のように、小さなグループを作って言葉のようにしてみるのも効果的です。いずれにしても全体に16分音符がばたばたとしないように、指を動かしすぎず、澄んだ音で流れていくようになるといいですね。
また、8分音符のモティーフのうち、カッコーのテーマはよく音を聴いて、「カッコー」と聞こえるようにいろいろと試してみましょう。
さらに、☆印の箇所などにみられるカッコーのテーマ以外の8分音符は、終止形またはそれに類するものを担当しているので、拍のうら・おもてをよく見ながらきれいなdim.を研究してみるとよいと思われます。
例えば「ボン・ジュール」の「ボン bon」や「オ eau(=“水”の意味)」のようなフランス語の1音節の言葉は、短いながらも後ろに余韻を持っているような言葉が多いので、この曲の8分音符もあまり短くしすぎず、フランス語のような響きを真似してみましょう。
フランス式の「トリル」
よくトリルを「その音から始めるのか」「ひとつ上の音から始めるのか」が議論になりますが、このころのフランス式のトリルは、原則として書かれた音の「ひとつ上の音から始める」のが基本です。このやり方は強拍に効果的な「不協和音」を生み出すのが特徴で、弾くときにそのことを意識して弾くと楽しくなってきます(ちなみにバッハもこのフランス式トリルの大いなる愛好者でした)。
フランス式のトリルの場合、ひとつ前の音が1音高い音で、しかもトリルのついた音があまり強い拍でない場合、前の音からかけられたスラーによってトリルの開始音が前の音とタイになってしまう特別なトリルがありますが、『バロック・アルバム』のこの曲の脚注bにその演奏方法が正しく示されていますので、参考にされるといいでしょう。
自然の中の音(この場合カッコーの鳴き声)に「耳を傾ける」というこの曲の性格は、とりもなおさず「音をよく聴く」という演奏の基本ともいうべきことと自然につながってくるので、音楽教育の現場でも大切にしていきたい曲のひとつです。ひとつひとつの音を大事に弾きながら、浮かび上がってくる繊細な響きによく耳を傾けたいですね。

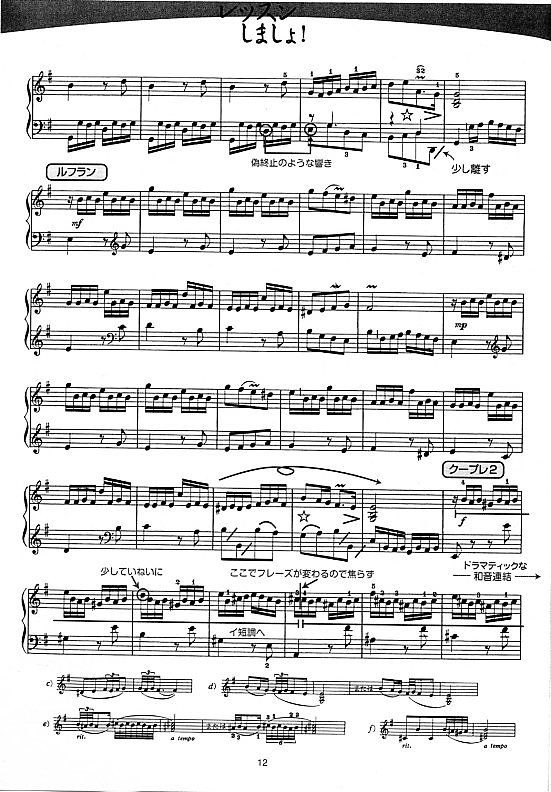
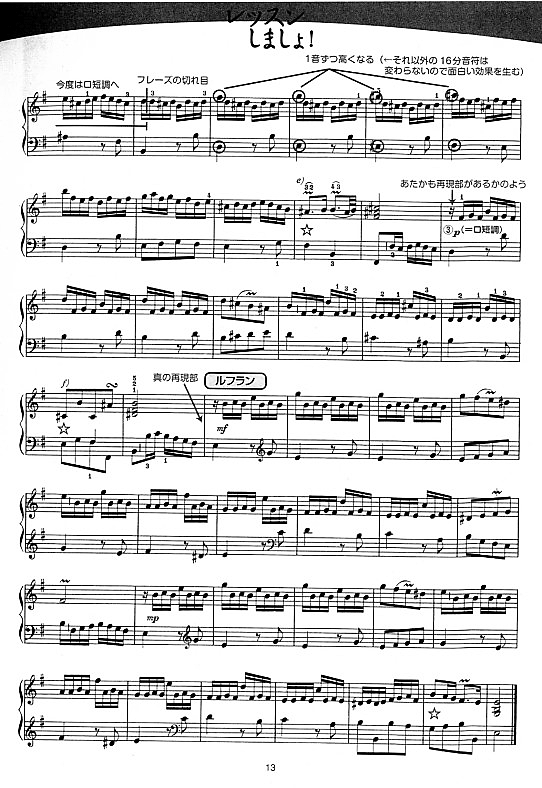
『MUSICA NOVA』 2009年4月号
|