|
バッハ音楽へのアプローチ
バッハの音楽はなぜ偉大? 演奏のコツとは?
若いころからの勉強家
かつて学校の音楽室の壁に並んでいた作曲家の肖像画の列、よくバッハ氏から始まっていて、「バッハは音楽の父です」などと説明されることもしばしば。もちろんバッハより前にも音楽はあったのでやや不思議な言い方ですが、なんでこんなふうに呼ばれるようになったのでしょうか。
そもそも、バッハは「始まり」なのか「終わり」なのか、ということについていろいろなことが言われてきました。たとえば「バッハは一つの終局である。彼からは何ものも発しない」といったのは有名なシュヴァイツァーでした。バッハにはそれ以前の音楽がすべて流れ込み、そしてバッハの中でひとつの大きなものにまとめあげられる、といったイメージでしょうか。
若いころのバッハについて書かれたものを読むと、ブクステフーデやラインケンらのあこがれのオルガニストの演奏を聴きに遠出した話や、高校生のときに本場フランスの楽団の演奏に触れて舞曲を学んだというような実演から学んだ話もたくさん出てきますが、とりわけ楽譜からいろいろな作曲家の書法を貪欲に学んだバッハの姿が強く浮かびあがってきます。フレスコバルディの『音楽の花束』、ヴィヴァルディらの協奏曲、ペルゴレージの『スタバトマーテル』などなど、いろいろな時代や国の興味深いたくさんの楽譜が筆写されてバッハの「楽譜棚」にあったことがわかっています。吸収するということにかける思いは並々ならぬ強さがあったようです。
「かけあわせ」が上手なバッハ
バッハが誰かの作品を学びそこから影響を受けるときにはそのままではなく、たいてい何かをつけ加えながらバッハらしいものを生み出すことが多い、と言われています。たとえば、若いころのバッハはたくさん他の作曲家のフーガを筆写して勉強するのですが、そのときにテーマだけ使って後は自分で変えてみたり、あるいは元の曲にはないエピソード部(間奏)を挟み込んでみたりしています。またこのフーガという形式を最新流行の「協奏曲」の形式とかけあわせて「協奏フーガ」と今では呼ばれる形を研究したりもしています。そういえば、前述のペルゴレージの『スタバトマーテル』をドイツ語のカンタータに仕立てあげたときには、原曲にはない素敵なヴィオラのパートがつけ加えられていましたっけ。そんな風に見ていくと、バッハ独自のとても「和声的」な「対位法」も、また「イタリア様式」と「フランス様式」が上手にミックスされた彼の鍵盤曲も、「かけあわせ」上手なバッハの本領発揮と言えますし、また本来「世俗」のものである「カンタータ(レチタティーヴォとアリアからなる)」という形式が「宗教曲」に用いられているなどということも、とてもバッハらしいことだと言えましょう。このような何かと何かをかけあわせてひとつのものにしてゆく「統合するバッハ」(M.ゲック)というのは、確かにバッハの芸術活動のひとつの重要な側面なのです。
その一方でバッハは「まとめ」「終わり」ばかりではありません。バッハを「開拓者」と呼んで、その「始まり」の側面を強調したのはベッセラーという学者でしたが、それ以降の作曲家に与えた影響という点でやはりバッハは特別の存在。バッハ独自の和声法や対位法はもちろん、独特の動機労作の方法、そして旋律法など、古典派やロマン派の作曲家たちがバッハから学んだことは大きかったのです。それまでの音楽の「まとめ」のような存在でもあったからこそ、後の音楽家にとって「栄養豊富な」存在でもありえたのでしょう。
なぜ鍵盤曲は難しい!?
さて、そのようなバッハの「偉大さ」を感じつつ、よりバッハを近く感じて弾きたいところですが、バッハの鍵盤曲はなんだか難しい、厳格な感じでノリにくい、歌いにくいという人も多いかもしれません。それもそのはずで、実はやはりバッハの場合、独奏曲が一番ややこしいのです。たとえば、バッハ独特の、同じリズムを巧みにたたみかけながら、まるでどこかに颯爽と連れていってくれるかのような爽快なリズム感、これを味わうには『ブランデンブルグ協奏曲』や『ヴァイオリンとチェンバロのソナタ』のようなアンサンブル曲が一番わかりやすいでしょう。
また、バッハの音楽の中で「人間らしい感情」に出会いたいと思ったら、なんといっても『マタイ受難曲』。この大作の中では次々と登場する人物の、喜んだり、泣いたり、耐えたり、納得したりといった心の動きが音楽で表され、そして聴くものが「共感」できるように仕組まれています。『マタイ』を聴いた後でバッハの他の作品を同じように眺めてみると、実はあちこちに同じような人間らしい心の動きが感じられることに気づかれることと思います。
それに比べると、鍵盤曲、リュート曲、無伴奏ヴァイオリンやチェロの作品など、ひとつの楽器のために書かれた一連の作品は、アンサンブル曲や声楽の作品に比べれば、歌詞や演奏用途などの制約も少なく、バッハ自身の自由なファンタジーが駆使され、いろいろなものをかけあわせる例のバッハお得意の「統合」の度合いも高くなるのです。いろいろな要素が目まぐるしく展開する豊かな世界、だから「難しい」と思う人がいても不思議はありません。
多義的で、少し抽象的で、しかもある意味何でもありの「鍵盤」の世界。ちょうどデパートのようなものでしょうか。デパートを適当に駆け足でまわっても全体像がよくわからないように、時間をかけてひとつひとつのお店をちゃんと見ることもバッハの場合には必要です。
難しい鍵盤曲にアプローチするには
たとえば、よく弾かれる『イタリア協奏曲』や『フランス風序曲』、どちらもふつうに考えればオーケストラ用の作品のタイトルです。それをあえて鍵盤曲として作曲し、そして「イタリア趣味 vs フランス趣味」の構図を鮮明に打ち出してひとつの楽譜集「クラヴィーア練習曲集第2部」にまとめて出版したバッハの心意気。弾くほうとしては、元のイタリア風のオーケストラや、フランスのバレエ用の楽団の音楽も知らないと、バッハの創意工夫を感じ取ることは難しいはず。また『半音階的幻想曲』の中に「レチタティーヴォ」と書かれているところがありますが、バッハの受難曲やカンタータのレチタティーヴォを知らないで弾くのはもったいないと思いませんか。
また、少し視点を変えて音符を眺めてみると、バッハは1本の旋律線の中にしばしば複数の声部を書き込んでいるのに出会います。たとえば、【譜例1】では二声部が、また【譜例2】では三声部がひとつの旋律線として描かれています。これもまた別の意味で「統合」されたものなわけで、このような隠れた声部進行を解きほぐすのは謎解きのような面白さがあります。バッハは24の調全部で書いてしまうことなどにも見られるように、どちらかというと「しつこい」気質。弾くほうも少ししつこい目にアプローチする必要があるかもしれません。
頭から、骨ごと!?
こんなふうに「統合」するのが好きなバッハですから、弾く人も声楽曲(カンタータや受難曲)と器楽曲(鍵盤曲や協奏曲など)を分けて勉強するのはもったいないし、また鍵盤でもたとえば、クラヴィーア(チェンバロ、クラヴィコード、ピアノなど)曲とオルガン曲を分けて勉強するのも、ソロとアンサンブル(通奏低音)を分けて勉強するのも残念……。というより、バッハの様子のわかる資料を読めば読むほど、こういった「分ける」勉強の仕方は「バッハらしくない」学び方のようなのです。案外いろいろな情報がわかっているので、その気になれば、バッハの貪欲に学んだ尊敬する先輩作曲家の作品を勉強してみることもできますし、バッハ先生のレッスンメソッドも指の使い方も体験できます。また少年合唱隊員としての歌っていたバッハ、フランス楽団にあわせてクーラントやメヌエットなど「舞曲」を踊る高校生のころのバッハなど、想像力の中でいろいろなバッハを追体験することも可能なのです。
もしかしたらこんなふうに、分けないで「あたまから、骨ごと」かじるのがバッハをより深く理解する何よりのコツなのかもしれません。
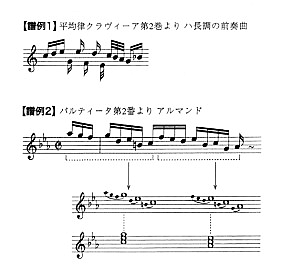
『ショパン』 2009年4月号
|